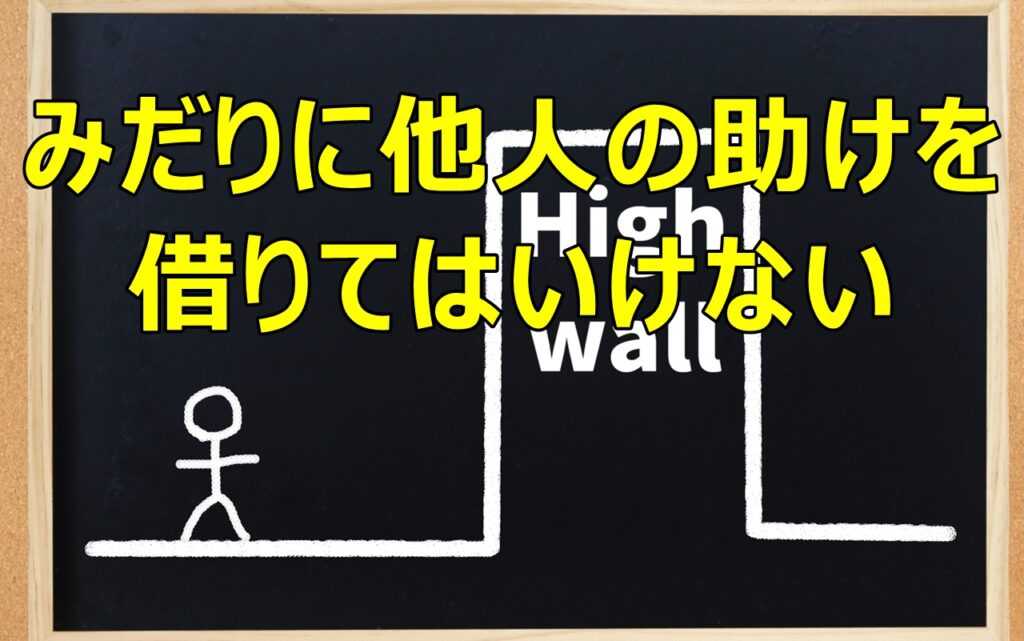不満をこぼしたいからこそ弱者の立場に身を置くのだ。
2021年12月1日「いや、違う。被害者でいるほうが楽なのだ。
弱者だから不平を言うのではない。
不満をこぼしたいからこそ弱者の立場に身を置くのだ。
彼らは望んで『弱者』になるのだよ」
タクティクスオウガとは

『タクティクスオウガ』とは、1995年にクエストから発売されたシミュレーションRPGです。『伝説のオウガバトル』に続くオウガシリーズ二作目で、ゲーム企画の松野泰己氏がスクウェアに移籍したことでも当時、話題になりました。
大まかな内容は西洋ファンタジーに政治、宗教、歴史など複雑な要素が盛り込まれた、重厚なストーリーのゲームです。
詳しい解説はウィキペディアへ
格言の自己解釈 不満をこぼしたい
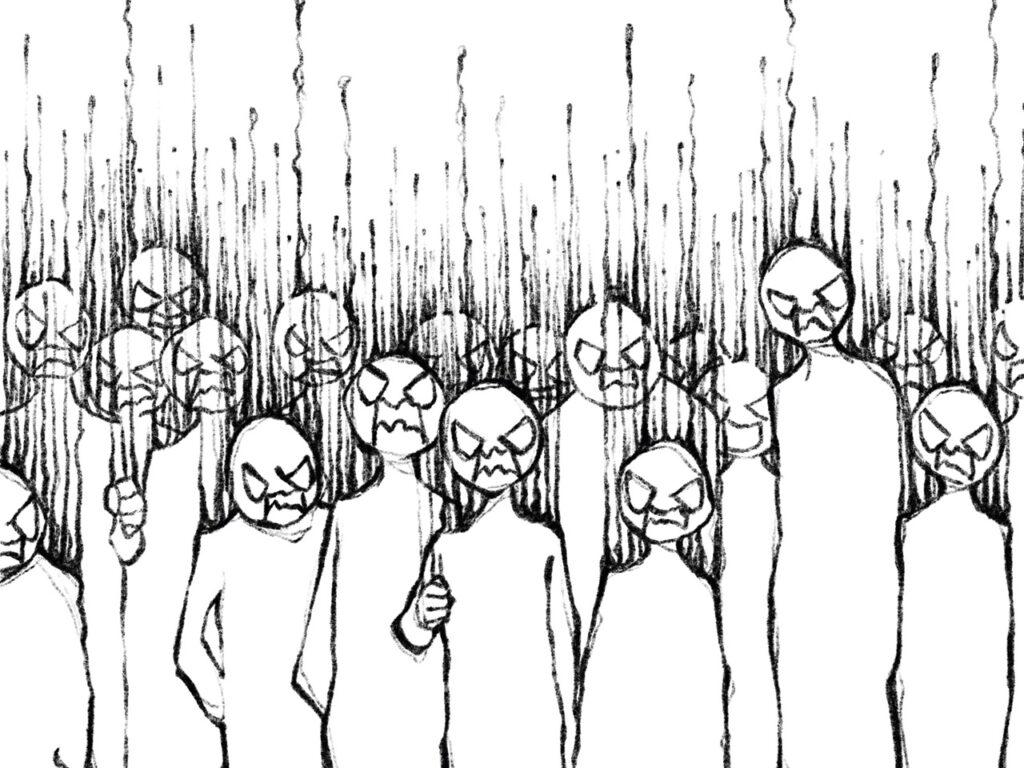
ゲームの中で聖騎士ランスロット・ハミルトンと暗黒騎士ランスロット・タルタロスが会話する中に、この言葉が出てきました。
聖騎士が力で民衆を縛り付けることは問題だと訴えたのに対して、暗黒騎士が民衆は力で支配されることを望んだと語ります。
人は自分が望まない環境にいるとき、不平や不満をこぼします。
自分は頑張っている、努力している、一生懸命生きている。
それでも自分は「弱者」だからこの状況から抜け出せない。
「弱者」だからこの状況に甘んじるのは仕方ないのだと言い訳をする。
しかし、真実はそうではない。
人はリスクを冒す勇気がないのだ。
リスクを冒して失敗したら、それは全て自己責任になる。
そこには自分に言い訳する逃げ道がなくなる
だから人は「弱者」であろうとし続ける。
「弱者」であるうちは環境的にはつらい思いをするが、精神的には逃げ道があることで救われる。
「弱者」であれば自分たちはリスクを冒さなくても、行動しないことを正当化していられる。
これこそが、人が不平・不満を言いながらも行動しない理由だと、聖騎士に突き付けている言葉だと感じました。
格言から学ぶこと
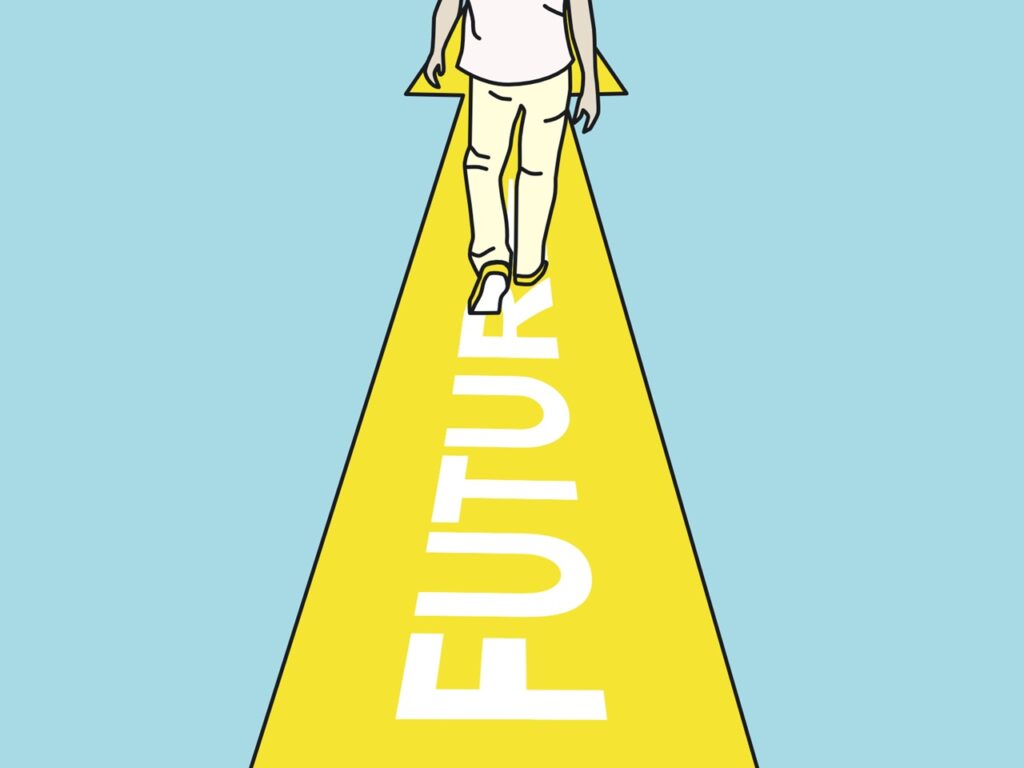
最近よく聞く言葉で「努力できるのも才能だ」というものがあります。
この言葉を聞いたとき「そこまで自分が行動しないことを正当化するのか…」と感じました。
私は「弱者の暴力」というものを感じる時が多々あります。
「弱者」の中には、「本当の弱者」と「弱者であろうとしている人」がいると思っています。
その「弱者であろうとしている人」は自分が弱者でありつづけることで、不満を言うこと、誰かを批判すること、行動しないこと、助けを待っていることを正当化しようとします。
そして自分が弱者だと正当化することで、リスクを冒して行動している人を阻害しようとする。
そこには「弱者」という免罪符があるため、攻撃することが正当化される。
「私たち庶民は…」、この言葉は本当に苦手です。
不満をこぼしたい人へ…
社会人になってから、色々な場所で不平や不満を聞くようになりました。
そのようなときに感じるのは「その不満を言うエネルギーで行動すれば、少しは状況を改善できるのでは?」ということです。
しかしほとんどの場合、「そうは言っても…」とすごいエネルギーで言い訳を聞かされることになります。
私は本当に失敗続きで、決して成功していません。
しかしその結果は自分の責任であって、他の誰かが悪いわけではありません。
自分的には「まだ成功していない」だけで、チャレンジ中と認識していますが…。
若いころは「自分は守ってもらうべき存在」と語る人達に、何か違和感を覚えていました。
行動できない自分に腹立たしさは覚えていましたが、それができなくて当然とは考えられませんでした。
そんなときにゲームでこの言葉を読んで「これが人の本質なのかも…」と感じました。
彼らは満たされていないから不満をこぼしているのではない。
不満を言う立場に身を置くことで満たされているのだ。
そう考えると、他人の不満話につきあうことがとても無駄な時間だと思うようになりました。
相談と不満は違います。
相談する人は、きっかけがあれば行動します。
不満を語る人は、きっかけがあっても徹底的に否定します。
相談には真摯に答えていこう、不満とは距離を取ろう。
そうしないと自分が知らないうちに、不満を言う側に回ってしまうかもしれない。
いろんな意味で私の価値観を決定づけた格言です。
投稿者プロフィール

- サイト制作者
-
人生の失敗を繰り返して、それでも元気に頑張っています。
仕事では、企業内の勢力争いに巻き込まれて左遷されたり、起業に失敗して借金を背負いました。
数々の失敗を自らの糧としながら借金を全額返済して、新しいスタートに取り組んでいます。
失敗や学びから人間の心理を勉強して、生きていくためのヒントを見つけていきます。
最新の投稿
 夫婦2022.07.25細かいことを気にする女性!その理由は見えない敵?
夫婦2022.07.25細かいことを気にする女性!その理由は見えない敵? 恋愛2022.07.13ときめきで感じさせる恋心!非日常で恋愛モードに切り替えろ
恋愛2022.07.13ときめきで感じさせる恋心!非日常で恋愛モードに切り替えろ 仕事や職場2022.07.06ボトルネックを探せ!生産性をアップさせる方法を紹介
仕事や職場2022.07.06ボトルネックを探せ!生産性をアップさせる方法を紹介 格言2022.06.26男は女の最初の恋人になりたがるが、女は男の最後の恋人になりたがる。
格言2022.06.26男は女の最初の恋人になりたがるが、女は男の最後の恋人になりたがる。